Report / Media
お知らせ
「アンコンかるた」:パナソニック インダストリー株式会社
- 導入事例

【富山県】「あなたにも思い込み『アルカモ』!?キャンペーン」に監修者として携わらせていただきました(2023年11月20日)
- メディア/執筆
- 導入事例

【こんにちは富山県です / 北日本放送 | KNB 】「アンコンシャスバイアス授業」の様子が、とりあげられました(2023年8月23日)
- メディア/執筆
- 子どもたちへ
- 導入事例

【都政新報】代表理事の守屋智敬が取材をうけました(2023年7月14日発行)
- メディア/執筆
- 導入事例

青山学院初等部でのアンコンシャスバイアス授業
- 講演/研修
- 子どもたちへ
- 導入事例

【日経ビジネス】パナソニックさんにおける「講師養成」のご支援について、取材をいただきました(2022年3月18日)
- メディア/執筆
- 導入事例

三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)社員の子どもたちへ、ワークショップを実施
- プレスリリース
- 子どもたちへ
- 導入事例

創業100年をこえる総合住宅資材企業「ヤマガタヤ」さまでの研修
- 導入事例
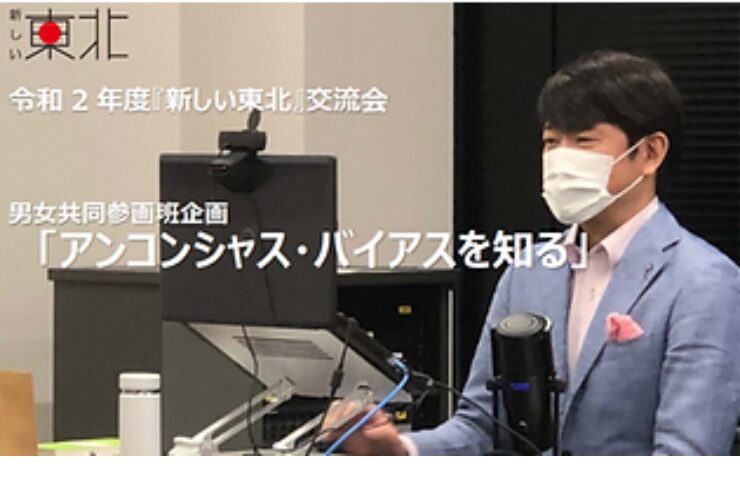
【復興庁HP】復興庁が開催する『新しい東北』交流会で、守屋が登壇しました(2021年3月)
- 講演/研修
- 導入事例
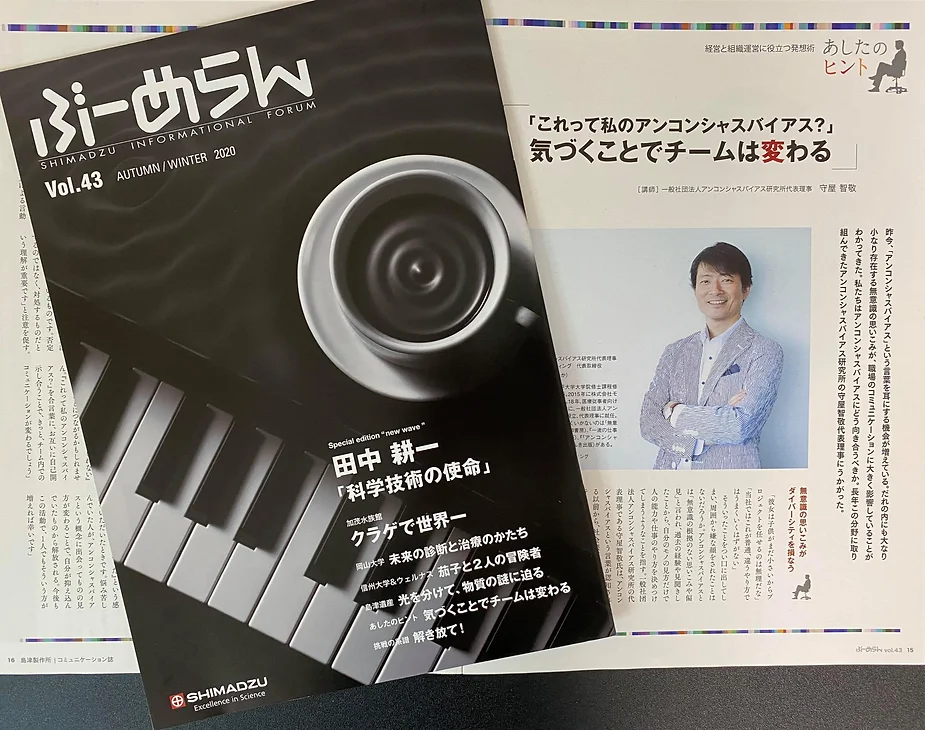
島津製作所でのオンラインセミナー。はじまりは、広報誌「ぶーめらん」からの取材依頼でした。
- メディア/執筆
- 導入事例

北海道大学の教職員の皆さんへ、「アンコンシャスバイアス」をお届けしました。
- 講演/研修
- 導入事例

広島県庁の管理職の皆さんへお届けした「アンコンシャスバイアス」講演会
- 講演/研修
- 導入事例
